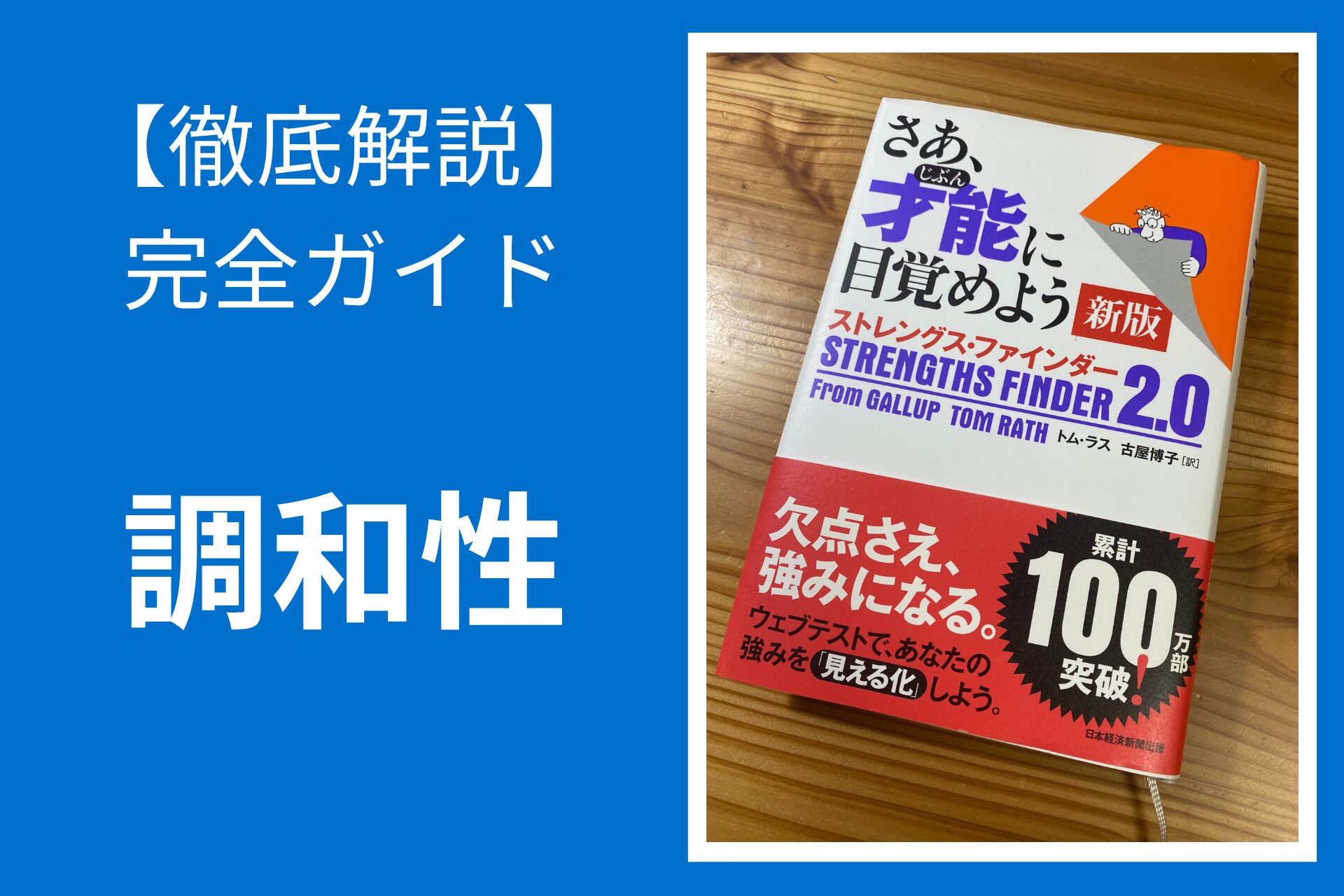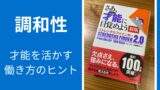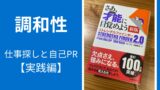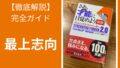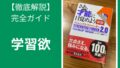「『調和性』って、一体どんな才能なんだろう?」
「『調和性』は、仕事や生活の中でどう活かせるのかな?」
ストレングスファインダー(クリフトンストレングス®)の診断をして、そんなふうに感じた方も多いかもしれませんね。
この記事では、あなたの「調和性」を活かすヒントをお届けします。
その才能がさらに輝くよう、一緒に見つけていきましょう。
💡この記事でわかること
✅ 「調和性」とは何か、その資質が持つ素晴らしい可能性
✅ 「調和性」が強みとして輝く「バルコニー」の状態と、具体的な行動例
✅ 知っておきたい「調和性」の注意点「ベースメント」と、その対策
ストレングスファインダー「調和性」の強みを自覚する第一歩
「調和性」という資質について、詳しく見ていきましょう。
「周囲と波風を立てたくないだけなのかな?」
「自分の意見がないタイプ?」
そんなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんね。
でも、これは大きな誤解です。
ここでは、「調和性」の本質的な特徴と、あなたの才能の源を明らかにしていきます。
ストレングスファインダー「調和性」の特徴
「調和性」の特徴は、対立を避け、みんなが納得できる道を探す力にあります。
意見がぶつかり合いそうな場面では、感情的な衝突を避けながら、両者の共通点や妥協点を探します。
そんなあなたの働きかけで議論が落ち着き、場に穏やかな空気が戻ったときには、大きなやりがいと安心感を感じるでしょう。
一方で、感情的な対立や、白黒つけるための議論ばかりの環境では、心が消耗し、強いストレスを感じるかもしれません。
この「無駄な対立は避けたい」「穏便に物事を進めたい」という思いこそが、「調和性」の原動力と言えるでしょう。
💡「調和性」のポイント
✅ 対立を避け、「共通点」や「落としどころ」を見つける
✅ 争うよりも、穏やかな合意形成を重視する
✅ お互いを尊重し合う、協力的な雰囲気をつくる
この資質は、あなたと周囲に穏やかさと協力をもたらしてくれる素晴らしい才能です。
「調和性」の才能を持つ人の行動・思考パターン
「調和性」の才能をお持ちの方には、日常の中で自然と現れる行動や思考があります。
ご自身にも当てはまるものがないか、ぜひチェックしてみてください。
💡「調和性」あるある行動・思考パターン
✅ 意見が対立しそうになると、自然と仲裁役になっている
人と人との間で、共通の土台や合意できる点を探そうとします。
✅ 周囲の人の表情や声のトーンから、場の空気を敏感に察知する
全体の調和を大切にし、誰もが心地よくいられるように気を配ります。
✅ 自分の意見を主張するより、人の話を聞くことが多い
全体の意見を把握してから、実用的で円満な解決策を考えようとします。
✅ 「波風を立てずに、平和的に済ませたい」と考える
感情的な衝突や不必要な競争よりも、平和で協力的な関係を好みます。
✅ みんなが納得できる落としどころを見つけるのが上手
理想論よりも、皆が合意しやすく、実際に機能する方法を重視します。
「調和性」の価値とは?その魅力と可能性
では、ストレングスファインダーにおいて、「調和性」が魅力ある才能といわれるのはなぜでしょうか。
それは、この資質が、チームに安定と協力的な関係をもたらす大きな力を持っているからです。
「調和性」を持つ人は、まず個々の感情や立場に寄り添い、対立の芽を摘んでいきます。
そして、その姿勢がチームに安心感を生み出し、誰もが安心して意見を言える空気をつくります。
また、多様な意見の中から共通点を見つけ出し、全員が納得できる着地点へと導くことも「調和性」の特徴です。
その働きにより、個人間の摩擦は減り、チームは一丸となって目標達成に向かうことができるでしょう。
✨「調和性」の魅力と可能性
✅ 異なる意見の橋渡しをして、前向きな合意に導く
✅ 安定した人間関係を築き、協力しやすいチームの雰囲気をつくる
✅ 誰もが受け入れやすい、実用的で現実的な解決に導く
強みの発揮!ストレングスファインダー「調和性」バルコニー状態の活かし方
「調和性」が持つ素晴らしい可能性について、少しずつイメージが湧いてきたのではないでしょうか。
では、その才能を日常で輝かせるには、どうしたら良いのでしょう。
ここでは、「調和性」が理想的な形で発揮されている「バルコニー」の状態について、詳しく見ていきます。
「調和性」が活きる!バルコニー状態のサインとは?
「バルコニー」とは、ストレングスファインダーで資質が最も輝くポジティブな状態のこと。
明るいバルコニーのように、心が開放的で、生産性も高まっている状態を指します。
💡 「調和性」のバルコニーサイン
✅ それぞれの意見にじっくり耳を傾け、理解しようとしている
✅ 対立を恐れるのではなく、穏やかな心で人と向き合えている
✅ 全員の意見を踏まえた、建設的な「第三の案」を提案できている
このバルコニーで輝く「調和性」の姿、いかがですか?
もしかしたら、「そういえば、あの時の自分がそうだったかも」と、思い当たる瞬間があるかもしれませんね。
資質の二面性(バルコニーとベースメント)について知りたい方は、こちらの記事も合わせてご確認ください。
>> ストレングスファインダー上位資質は”強み”じゃない?|才能を真の強みに変える3ステップ
あなたの力を引き出す!「調和性」を育てる3ステップ
「調和性」がバルコニーで穏やかに輝いている状態、とても心温まるものですよね。
では、どうすれば、あなたのその素晴らしい才能をバルコニーで育てていけるのでしょうか。
ここでは、Gallup社が提唱する「Name it, Claim it, Aim it」という3つのステップに沿って、一緒に見ていきましょう。
ステップ1:Name it (見極める) ~あなたの「調和性」を特定する~
まずは、ご自身の「調和性」がどんな場面で顔を出すのか、その特徴を「これだ!」と見極めることから始めましょう。
「ここは波風を立てず、穏便に進めたいな…」
「みんなが納得できる着地点はないかな?」
そう感じる瞬間や、場の空気が和やかになるよう自然と振る舞っている時。
それは、あなたの「調和性」が働いている大切なサインです。
ご自身の行動や感情と丁寧に向き合うこと。
そして――
「これが私の調和性なんだ」と納得することが、自分らしく輝くための第一歩です。
ステップ2:Claim it (明確にする) ~「調和性」を自分のものと宣言する~
次に、その「調和性」を、かけがえのない「あなた自身の強みの一部」として、しっかりと受け止めましょう。
このステップでは、過去を振り返り――
「意見の対立を調整したからこそ、あの仕事は円滑に進んだんだ」
「みんなが安心して話せる場を作ったことが、チームの力につながった」
など、この「調和性」がどのようにポジティブに働いてきたかを明確にしていきます。
自分の強みが、過去のうまくいった経験にどう貢献してきたかを理解すること。
それが、ゆるぎない自信へとつながっていきます。
「自分の意見を抑えすぎかな」と感じたことがあったとしても、それも「調和性」の一部です。
まずは、そんな自分を責めずに、まるごと受け入れてあげましょう。
ステップ3:Aim it (狙う) ~「調和性」を意図的に活かす~
最後は、「調和性」を、これからの仕事や日々の生活の中で、意図的に活かしていくステップです。
「この会議では、異なる意見の橋渡しを意識しよう!」
「チームの意見がぶつかりそうなとき、自分が潤滑油になろう」
と、具体的な活かし方を考えて行動に移してみましょう。
その際は、周囲に合わせすぎて自分の想いを置き去りにしないよう、「今、何を大事にしたいか」を意識しておきたいですね。
また、対話を重んじる風土のある環境に身を置くことも大切です。
自分の強みを活かせる役割や仕事に意識的に時間を使うことで、「調和性」はさらに輝きを増していくでしょう。
「調和性」の強みを発揮しやすい環境については、こちらの記事で解説しています。
よろしければ、ぜひ合わせてご覧ください。
>> 【調和性】キャリアの羅針盤:今の仕事への活かし方と、未来の可能性を見つけるヒント
🌿「調和性」を強みに育てる3ステップ
✅ Name it (見極める):
日頃の「調和性」の働き(合意形成や調整行動など)に気づき、「これがそうか」と認識する
✅ Claim it (明確にする):
「周囲との関係を円滑に保ったことが、良い結果につながった」経験を思い出し、自分の才能として受け入れ、自信へとつなげる
✅ Aim it (狙う):
人間関係の円滑化やチームでの合意形成のために、「調和性」を意図的に活用していく
要注意!ストレングスファインダー「調和性」ベースメントとその対策法
どんな素晴らしい才能も、時にはその輝きが曇り、裏目に出てしまうことがあります。
ストレングスファインダーでは、こうした状態を「ベースメント(地下室)」と呼びます。
ご自身のベースメントの傾向を知ることは、「調和性」を上手に活かす上で大切なステップです。
このセクションでは、「調和性」の注意点である「ベースメント」状態と、その対策法について見ていきましょう。
「調和性」の落とし穴?ベースメント状態を解説
ベースメントとは、あなたの資質がネガティブな形で顔を出してしまう状態のこと。
日当たりの良いバルコニーとは対照的に、薄暗く風通しの悪い地下室(ベースメント)をイメージすると分かりやすいかもしれませんね。
「調和性」がベースメントにあると、あなたの強みであるはずの「対立を避けて、みんなの納得点を探ろうとする姿勢」が、裏目に出てしまうことがあります。
例えば――
・自分の意見を飲み込んでしまい、心の中でモヤモヤを抱え込む
・問題の根本的な解決を避け、事なかれ主義に陥ってしまう
その結果、気づかぬうちにストレスを溜めたり、「自分の意見がない人」と誤解されてしまうこともあるかもしれません。
⚠️「調和性」のベースメント状態
✅ 意見や感情を抑え込みすぎて、知らないうちにストレスを溜めてしまう
✅ 対立を恐れるあまり、向き合うべき重要な問題から目を背けてしまう
✅ 周囲に合わせすぎて、主体性がない・本音が見えないと思われてしまう
資質を上手に使う!ベースメントへの具体的な対処法
では、ベースメント状態から「調和性」を再び輝かせるにはどうすれば良いでしょうか。
ここでは、ベースメントから抜け出し、「調和性」が持つ本来の良さを活かすためのアプローチを解説します。
💡 「調和性」ベースメントに賢く対処するコツ
✅ 「沈黙」ではなく、「穏やかな自己主張」を心がける
「調和性」は、対立を避けたいあまり、自分の意見を押し殺してしまいがちです。
自分の中の声に耳を傾け、穏やかに言葉を選んで伝えてみましょう。
声に出すことで、あなたの想いや視点が、理解や共感を生むきっかけになります。
✅ 「見て見ぬふり」ではなく、「前向きな関わり」を選ぶ
「調和性」は、問題を見過ごすことで場の空気を守ろうとする傾向があります。
持ち前のバランス感覚を活かして、皆にとって前向きな解決を一緒に考えてみましょう。
あなたの気づきが、チーム全体の改善につながっていきます。
✅ 「対立=悪」ではなく、「健全な意見交換の機会」と捉える
「調和性」は、意見の衝突に不安を感じて、距離を置いてしまうことがあります。
その感受性を活かし、お互いの立場や想いをすり合わせる視点を持ってみましょう。
あなたが間に入ることで、対立が「対話の機会」に変わる可能性があります。
✅ 「同調」しすぎず、「自分の軸」も大切にする
「調和性」は、周囲に合わせすぎて、自分の気持ちを見失ってしまうことがあります。
時には自分の判断軸に従い、丁寧に『NO』を伝えてみましょう。
あなた自身を大切にすることで、より深く信頼される存在になっていきます。
ベースメントとの向き合い方を学ぶことは、「調和性」と共に歩むための大切なプロセスです。
焦らず、あなたらしいバランスを見つけていきましょう。
実践!ストレングスファインダー「調和性」を覚醒させる活かし方戦略
「調和性」の輪郭、そしてその光と影の部分が、だいぶ見えてきたのではないでしょうか。
このセクションでは、あなたの「調和性」を、特に仕事の場面で活かすための戦略を一緒に見ていきましょう!
「調和性」を仕事で活かすヒント
あなたの「調和性」は、日々の業務を円滑に進め、チームの協力関係を育む力となります。
・異なる意見を持つ人々の間で、潤滑油のような役割を果たすこと
・チーム全体の合意形成をサポートし、協力的な雰囲気を作ること
これらが、職場でさらに貢献するためのカギとなるでしょう。
ふたつの職種を例に、具体的な活かし方をご紹介しますね。
💡【職種別】「調和性」仕事での活かし方事例
💼 営業パーソンの場合
顧客の声に耳を傾け、関連部署との調整も円滑に進めることで、Win-Winの提案を形にできます。
「全員が納得できる落としどころ」を見つける力が、信頼されるパートナーシップを築く助けとなるでしょう。
💻 事務スタッフの場合
チーム内の意見や情報を整理し、スムーズな連携が図れるようサポートすることで、円滑な業務運営に貢献できます。
日々の細やかな気配りが、チーム全体の安心感と働きやすさを高めていくでしょう。
「調和性」を活かしたキャリアをもっと考えたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
よろしければ、ぜひ合わせてご覧ください。
>> 【調和性】キャリアの羅針盤:今の仕事への活かし方と、未来の可能性を見つけるヒント
「調和性」をキャリアチェンジに活かすヒント
あなたの「調和性」は、新たなキャリアへ踏み出し、やりがいを感じる仕事を見つける際にも、大きな武器となります。
では、どんなステージ(職場)が「調和性」のあなたに合っているのでしょうか。
💡「調和性」が活きるステージ
✅ チームワークと協調性が尊重される環境
あなたの、異なる意見の間に立ち、円滑なコミュニケーションを促す力。
チームで協力して目標を目指す環境では、その価値が最大限に発揮されるでしょう。
✅ 安定したプロセスの中で実務的な貢献が求められる場所
急激な変化や競争よりも、決まった手順で着実に物事を進めることを好むあなた。
堅実な職場では、その丁寧な仕事ぶりが信頼を集め、安定した成果と満足感を得ることができるでしょう。
「調和性」の魅力を発揮できるキャリアチェンジを考えたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
よろしければ、ぜひ合わせてご覧ください。
>> 【調和性】転職成功の秘訣!強みを活かす仕事探しと自己PR術
人間関係を円滑にする「調和性」コミュニケーション
「調和性」は、自分だけでなく、相手の意見や感情にも注意を払い、穏やかで協力的な関係を築くことに長けた資質です。
その視点を活かせば、相互理解を深め、心地よい関係性を育むことができます。
💡「調和性」が活きるコミュニケーション
相手の話を最後まで聞き、安心感を与える
「調和性」のあなたは、相手の言葉にじっくりと耳を傾け、その背景にある思いや立場を理解しようと努めます。
あなたの穏やかな姿勢は、相手に安心感を与え、本音を引き出す信頼関係を育むでしょう。
感情的な衝突を避け、穏やかな合意点を探る
意見がぶつかりそうになった時も、あなたは冷静さを保ち、皆が納得できる現実的な解決策を見つけようとします。
その冷静でバランスの取れた対応が、建設的な対話を促すでしょう。
あなたの「調和性」は、周囲との関係をより円滑で心地よいものにする潤滑油となります。
意識して使ってみると、思っていた以上の信頼や絆が生まれるかもしれません。
ストレングスファインダー「調和性」に関するよくある質問(FAQ)
ここでは、「調和性」についてよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
A. 「調和性」と対照的な価値観を持つ資質として、「指令性(Command)」が挙げられます。
「調和性」は、人々の間の共通点を見つけ、対立を避けながら物事を前に進めようとします。
一方「指令性」は、意見の対立や議論を恐れず、それらを意思決定のための自然なプロセスと捉えます。
【アプローチの違い】
・調和性: 対立を避け、合意できる「共通点」を探す
・指令性: 対立点に踏み込み、議論を通じて「結論」を出す
このように、両者は対立への向き合い方が正反対ですが、どちらもチームを前に進めようとする、大切な才能です。
A. ストレングスファインダーの資質は、他の上位資質と組み合わさることで、強みの現れ方が大きく変わります。
「調和性」の場合、他の資質のエネルギーを対立ではなく「協力」や「合意」へと向けるように調整する、チームの潤滑油のような役割を果たします。
例えば、以下のようなイメージです。
・「調和性」×「分析思考」:
データや事実を冷静に分析する力が、感情的な対立を避け、客観的な根拠に基づいた「全員が納得できる着地点」を見つけるために使われます。
・「調和性」×「公平性」:
全員を平等に扱いたいという欲求が、対立を生まない、誰もが納得できる「現実的なルール」や「運用の仕組み」を築く力になります。
このように、ご自身の上位資質がどのように掛け合わさっているかを意識することで、あなただけのユニークな強みの活かし方が見えてきます。
まとめ:ストレングスファインダー「調和性」を活かし、自分らしい人生を描こう
「調和性」は、異なる意見や立場の間に橋をかけ、みんなが安心して協力できる場をつくる、素晴らしい才能です。
その穏やかな力は、あなた自身の心の安定につながるだけでなく、周囲にも安心感をもたらします。
ぜひ、この素晴らしい力を信じて、日々の選択や行動の中に意識的に取り入れてみてください。
もちろん、資質の活かし方に「正解」はありません。
今回ご紹介したヒントは、あくまで可能性のひとつです。
大切なのは、あなたが心地よく、そして最も自分らしく輝ける方法を、ご自身のペースで見つけていくことです。
ぜひ、「自分らしい調和性の活かし方」を見つけていってください。
あなたの「調和性」が、あなた自身とあなたの周りの世界を、もっと素敵に変えていくことを心から応援しています。
Use your strengths to be yourself.
~強みを活かして、あなたらしい人生を~
【合わせて読みたい「調和性」の関連記事】
・【調和性】キャリアの羅針盤:今の仕事への活かし方と、未来の可能性を見つけるヒント
・【調和性】転職成功の秘訣!強みを活かす適職探しと自己PR術
▼全34資質 解説記事一覧はこちら▼
| 実行力 | 影響力 | 人間関係 構築力 |
戦略的 思考力 |
|---|---|---|---|
| 達成欲 | 活発性 | 適応性 | 分析思考 |
| アレンジ | 指令性 | 運命思考 | 原点思考 |
| 信念 | コミュニケーション | 成長促進 | 未来志向 |
| 公平性 | 競争性 | 共感性 | 着想 |
| 慎重さ | 最上志向 | 調和性 | 収集心 |
| 規律性 | 自己確信 | 包含 | 内省 |
| 目標志向 | 自我 | 個別化 | 学習欲 |
| 責任感 | 社交性 | ポジティブ | 戦略性 |
| 回復志向 | 親密性 |
『ストレングスファインダー』は長年親しまれてきた名称ですが、現在は開発者の名を冠した『クリフトンストレングス®︎』が正式名称として使われています(提供元は変わらずGallup社)。
診断内容や考え方は同じものです。
この記事では、広く知られている『ストレングスファインダー』という言葉を用いますが、現在の正式名称は『クリフトンストレングス®︎』である点をご理解いただけますと幸いです。