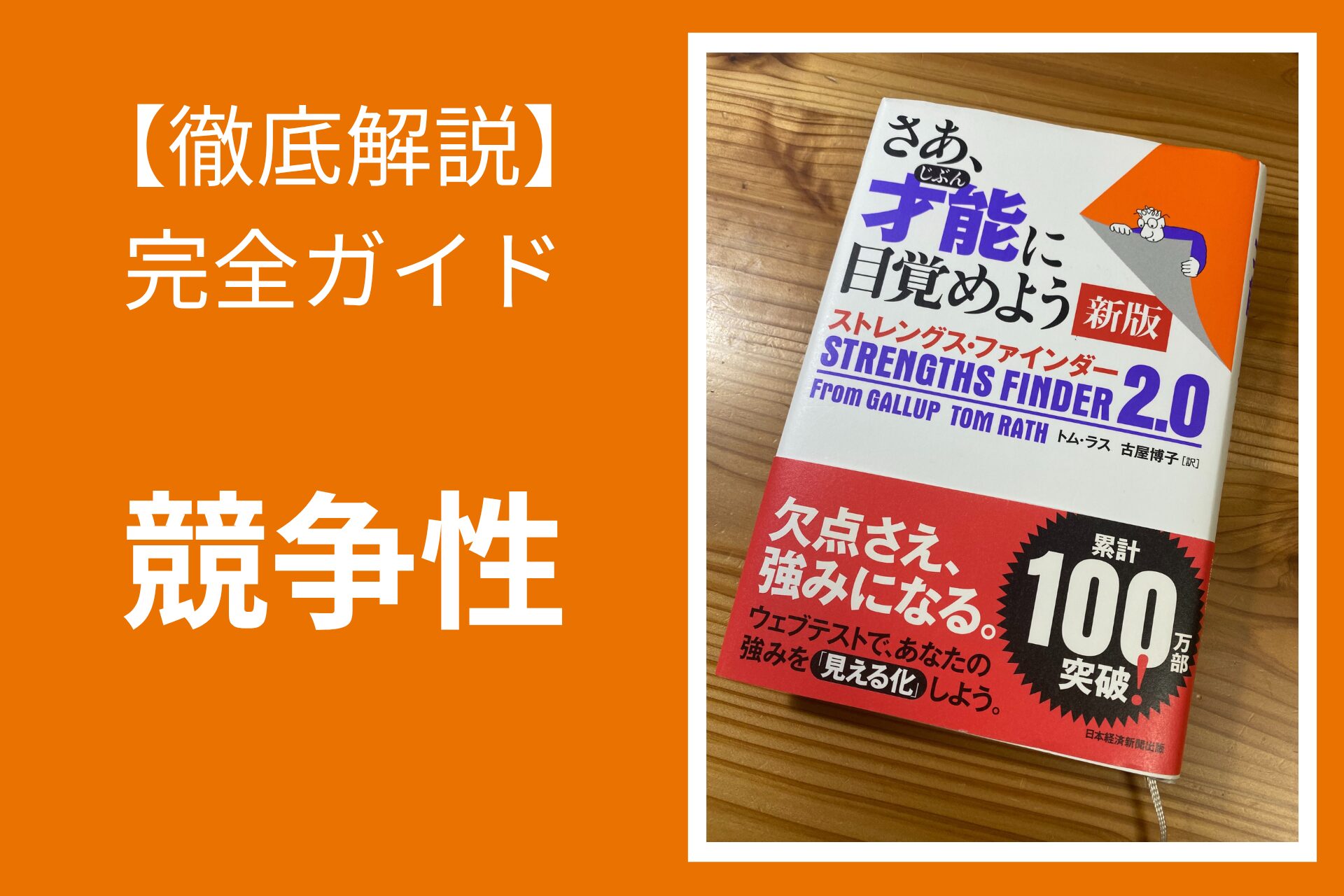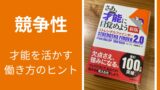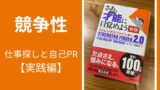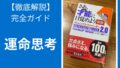「『競争性』って、一体どんな才能なんだろう?」
「『競争性』は、仕事や人間関係の中でどう活かせるのかな?」
ストレングスファインダー(クリフトンストレングス®)の診断をして、そんなふうに感じた方も多いかもしれませんね。
この記事では、あなたの「競争性」を活かすヒントをお届けします。
その才能がさらに輝くよう、一緒に見つけていきましょう。
💡この記事でわかること
✅ 「競争性」とは何か、その資質が持つ素晴らしい可能性
✅ 「競争性」が強みとして輝く「バルコニー」の状態と、具体的な行動例
✅ 知っておきたい「競争性」の注意点「ベースメント」と、その対策
ストレングスファインダー「競争性」の強みを自覚する第一歩
「競争性」という資質について、詳しく見ていきましょう。
「勝つためなら、手段を選ばない人?」
「何でも、勝ち負けでしか判断できない?」
そんなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
でも、これは大きな誤解です。
ここでは、「競争性」の本質的な特徴と、あなたの才能の源を明らかにしていきます。
ストレングスファインダー「競争性」の特徴
「競争性」の特徴は、他者との比較を通じて自分の位置を確認し、「勝ちたい」という強い衝動を成果につなげる力にあります。
常に「誰が一番か」という基準を探し、その順位づけがエネルギーの源になります。
明確なライバルが存在し、その相手に勝利した瞬間に、最高の満足感を得るでしょう。
一方で、勝敗が曖昧な状況や、比較する相手がいない環境では、モチベーションを維持するのが難しいかもしれません。
この「勝ちたい、一番になりたい」という情熱こそが、「競争性」の原動力と言えるでしょう。
💡「競争性」のポイント
✅ 勝敗や順位が明確な場面で力を発揮する
✅ 他者と比較することで、自分のエネルギーを高める
✅ 勝利した瞬間に、大きな充実感と喜びを感じる
この資質は、常に高みを目指し、チームを勝利へと駆り立てる、力強い「挑戦者」のような素晴らしい才能です。
「競争性」の才能を持つ人の行動・思考パターン
「競争性」の才能をお持ちの方には、日常の中で自然と現れる特徴的な行動や思考があります。
ご自身にも当てはまるものがないか、ぜひチェックしてみてください。
💡「競争性」あるある行動・思考パターン
✅ どんな些細なことでも、ゲーム感覚で勝ち負けをつけたがる
ただ参加するだけでは満足できず、必ず「誰が一番か」を決めたくなります。
✅ 自分の成績や順位を、常に他人と比較している
他者のパフォーマンスが「基準点」であり、その基準を超えることで、自分の成長と勝利を実感します。
✅ ライバルの活躍を聞くと、悔しさよりも闘志が湧く
他者の成功は、「自分も負けていられない」という、次なる勝利への強力なエネルギー源となります。
✅ 議論の場でも、つい勝ち負けを意識する
意見交換よりも、「どちらが正しいか」の決着をつけたい気持ちが先立ちます。
✅ 勝てないと分かる場面には、最初から挑まない
勝つことに意味があるため、明らかに勝ち目がない勝負には意欲が湧かず、エネルギーを注ぎません。
「競争性」の価値とは?その魅力と可能性
では、ストレングスファインダーにおいて、「競争性」が魅力ある才能といわれるのはなぜでしょうか。
それは、この資質が、「勝ちたい」という強い衝動を原動力に、チーム全体のパフォーマンスレベルを引き上げる力を持っているからです。
「競争性」を持つ人は、常に自分と他者のパフォーマンスを比較し、どうすれば勝てるかを考えています。
その姿勢は周囲に刺激を与え、「自分たちも負けられない」という健全な緊張感と向上心を生み出します。
さらに、この才能は、チームの士気が停滞している時にこそ力を発揮します。
「1位になる」「ライバルに勝つ」という明確で刺激的な目標を掲げることで、チームに再び挑戦の火をつけることができるでしょう。
✨「競争性」の魅力と可能性
✅ 現状に満足せず「もっとできる」という向上心をかき立て、チームの基準を引き上げる
✅ 「勝利」という明確な目標を掲げ、チームのモチベーションに火をつける
✅ パフォーマンスを測定可能なものとして捉え、組織の生産性を向上させる
強みの発揮!ストレングスファインダー「競争性」バルコニー状態の活かし方
「競争性」が持つ素晴らしい可能性について、少しずつイメージが湧いてきたのではないでしょうか。
では、その才能を日常で輝かせるには、どうしたら良いのでしょう。
ここでは、「競争性」が理想的な形で発揮されている「バルコニー」の状態について、詳しく見ていきます。
「競争性」が活きる!バルコニー状態のサインとは?
「バルコニー」とは、ストレングスファインダーで資質が最も輝くポジティブな状態のこと。
明るいバルコニーのように、心が開放的で、生産性も高まっている状態を指します。
💡 「競争性」のバルコニーサイン
✅ ライバルの存在を前向きな刺激とし、「負けられない」という闘争心でチームの士気を高めている
✅ 勝敗を客観的な指標で測定し、ゲームのように楽しみながら、チームを勝利へと導いている
✅ 個人の勝利だけでなく、チーム全体の達成をともに喜び、仲間の努力を称えている
このバルコニーで輝く「競争性」の姿、いかがですか?
もしかしたら、「そういえば、あの時の自分がそうだったかも」と、思い当たる瞬間があるかもしれませんね。
資質の二面性(バルコニーとベースメント)について知りたい方は、こちらの記事も合わせてご確認ください。
>> ストレングスファインダー上位資質は”強み”じゃない?|才能を真の強みに変える3ステップ
あなたの力を引き出す!「競争性」を育てる3ステップ
「競争性」がバルコニーで穏やかに輝いている状態、とても心温まるものですよね。
では、どうすれば、あなたのその素晴らしい才能をバルコニーで育てていけるのでしょうか。
ここでは、Gallup社が提唱する「Name it, Claim it, Aim it」という3つのステップに沿って、一緒に見ていきましょう。
ステップ1:Name it (見極める) ~あなたの「競争性」を特定する~
まずは、ご自身の「競争性」がどんな場面で顔を出すのか、その特徴を「これだ!」と見極めることから始めましょう。
「つい、自分の順位やスコアが気になってしまう」
「ライバルがいるからこそ、自分のベストが出せる」
そう感じる瞬間や、周囲が気楽に楽しんでいる場面でも、自分だけが無意識に勝ち負けを意識している時。
それは、あなたの「競争性」が働いている大切なサインです。
ご自身の行動や感情と丁寧に向き合うこと。
そして――
「これが私の競争性なんだ」と納得することが、自分らしく輝くための第一歩です。
ステップ2:Claim it (明確にする) ~「競争性」を自分のものと宣言する~
次に、その「競争性」を、かけがえのない「あなた自身の強みの一部」として、しっかりと受け止めましょう。
このステップでは、過去を振り返り――
「あの時、ライバルの存在があったから、自分の限界を超えることができた」
「『絶対に勝ちたい』という思いがあったから、最後まで粘り抜いて逆転できた」
など、この「競争性」がどのようにポジティブに働いてきたかを明確にしていきます。
自分の強みが、過去のうまくいった経験にどう貢献してきたかを理解すること。
それが、ゆるぎない自信へとつながっていきます。
「勝ちにこだわりすぎて、周りを不快にさせてしまったかも」と感じたことがあったとしても、それも「競争性」の一部です。
まずは、そんな自分を責めずに、まるごと受け入れてあげましょう。
ステップ3:Aim it (狙う) ~「競争性」を意図的に活かす~
最後は、「競争性」を、これからの仕事や日々の生活の中で、意図的に活かしていくステップです。
「次のプロジェクトでは、ライバルを設定し、互いに高め合える関係を築こう」
「チームの進捗を『見える化』して、ゲーム感覚で目標達成を楽しもう」
と、具体的な活かし方を考えて行動に移してみましょう。
その際は、「勝つこと」だけにとらわれるのではなく、その勝利がチーム全体や組織の成果につながるかどうかを意識したいですね。
また、売上目標が明確な営業職や、コンペ形式で提案を行う仕事など、成果が比較される役割を積極的に担うのも効果的です。
自分の強みを活かせる役割や仕事に意識的に時間を使うことで、「競争性」はさらに輝きを増していくでしょう。
「競争性」の強みを発揮しやすい環境については、こちらの記事で解説しています。
よろしければ、ぜひ合わせてご覧ください。
>> 【競争性】キャリアの羅針盤:今の仕事への活かし方と、未来の可能性を見つけるヒント
🌿「競争性」を強みに育てる3ステップ
✅ Name it (見極める):
自分の順位が気になったり、「相手がいるから頑張れる」と感じた瞬間に、「これがそうか」と認識する
✅ Claim it (明確にする):
過去に、ライバルの存在によって限界を超えたり、「勝ちたい」一心で最後まで粘り抜いたりした経験を思い出し、自分の才能として受け入れる
✅ Aim it (狙う):
チームや自分の目標達成のために、健全な競争環境を意図的に作り出し、勝利へのエネルギーを成果に変えていく
要注意!ストレングスファインダー「競争性」ベースメントとその対策法
どんな素晴らしい才能も、時にはその輝きが曇り、裏目に出てしまうことがあります。
ストレングスファインダーでは、こうした状態を「ベースメント(地下室)」と呼びます。
ご自身のベースメントの傾向を知ることは、「競争性」を上手に活かす上で大切なステップです。
このセクションでは、「競争性」の注意点である「ベースメント」状態と、その対策法について見ていきましょう。
「競争性」の落とし穴?ベースメント状態を解説
ベースメントとは、あなたの資質がネガティブな形で顔を出してしまう状態のこと。
日当たりの良いバルコニーとは対照的に、薄暗く風通しの悪い地下室(ベースメント)をイメージすると分かりやすいかもしれませんね。
「競争性」がベースメントにあると、あなたの強みであるはずの「勝利へのエネルギー」が、裏目に出てしまうことがあります。
例えば――
・勝つことにこだわりすぎて、仲間さえも「打ち負かす相手」と見なしてしまう
・自分が勝てない状況になると、不機嫌になったり、相手の成功を素直に認められなかったりする
その結果、周りからは「協調性に欠ける」「ただの負けず嫌い」と受け取られ、せっかくの推進力がチームの和を乱す要因になってしまうかもしれません。
⚠️「競争性」のベースメント状態
✅ 仲間をライバル視しすぎて、健全な協力関係を築けない
✅ 自分の勝利にしか価値を見出せず、他者の成功を素直に喜べない
✅ 勝ちに執着するあまり、ルールや倫理観を軽視してしまう
資質を上手に使う!ベースメントへの具体的な対処法
では、ベースメント状態から「競争性」を再び輝かせ-るにはどうすれば良いでしょうか。
ここでは、ベースメントから抜け出し、「競争性」が持つ本来の良さを活かすためのアプローチを解説します。
💡 「競争性」ベースメントに賢く対処するコツ
✅ 「社内のライバル」だけでなく、「本当の競合」に目を向ける
「競争性」は、身近な同僚をライバルと見なしてしまい、チーム内の協力関係を損なうことがあります。
その闘争心を、社外の競合他社という、チーム共通の「敵」に向けてみましょう。
社内の競争は、外で勝つための健全なトレーニングと捉えることが大切です。
✅ 「個人の勝利」だけでなく、「チームの成功」を喜ぶ
「競争性」は、個人の成果だけに固執するあまり、仲間の成功を素直に喜べなくなることがあります。
「チームの勝利における、自分の役割は何か」を考えてみましょう。
チーム全体の成功に役立った実感が、あなたの勝利をより価値あるものにします。
✅ 「勝敗の結果」だけでなく、「フェアな過程」も大切にする
「競争性」は、勝ちに執着するあまり、手段を選ばなくなってしまう危うさがあります。
事前に「正々堂々と戦う」という自分なりのルールを定めておきましょう。
その姿勢が、あなたの勝利をさらに輝かせます。
✅ 「他人との比較」だけでなく、「過去の自分」との比較軸を持つ
「競争性」は、常に他者との比較で自分を測るため、相手がいないとモチベーションを失ったり、自信をなくしたりすることがあります。
「昨日の自分を超える」という、もうひとつの軸を持ってみましょう。
自己成長をゲームのように楽しむことで、ぶれない自信とモチベーションを維持できます。
ベースメントとの向き合い方を学ぶことは、「競争性」と共に歩むための大切なプロセスです。
焦らず、あなたらしいバランスを見つけていきましょう。
実践!ストレングスファインダー「競争性」を覚醒させる活かし方戦略
「競争性」の輪郭、そしてその光と影の部分が、だいぶ見えてきたのではないでしょうか。
このセクションでは、あなたの「競争性」を、特に仕事の場面で活かすための戦略を一緒に見ていきましょう!
「競争性」を仕事で活かすヒント
あなたの「競争性」は、「勝利」への強いこだわりをチームの力に変え、全体のパフォーマンスレベルを引き上げる起爆剤となります。
・チームが目指すベンチマークとして、具体的なライバル(競合他社など)を設定すること
・仕事の成果を「スコアボード」のように数値化・可視化し、チームの闘争心に火をつけること
これらが、仕事でさらに貢献するためのカギとなるでしょう。
ふたつの職種を例に、具体的な活かし方をご紹介しますね。
💡【職種別】「競争性」仕事での活かし方事例
💼 営業パーソンの場合
社内の営業成績ランキングや、競合他社の実績を常に意識し、「自分が一番になる」という強い意志で行動することができます。
その勝利への執着が、あなたをトップセールスへと押し上げ、チーム全体の目標達成を力強く牽引します。
💻 事務スタッフの場合
「誰よりも早く正確に処理する」「エラーゼロを継続する」など、自分なりの競争テーマを日常業務に設定できます。
その取り組みが、ルーティンワークにゲーム感覚をもたらし、チーム全体の効率と質を底上げするでしょう。
「競争性」を活かしたキャリアをもっと考えたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
よろしければ、ぜひ合わせてご覧ください。
>> 【競争性】キャリアの羅針盤:今の仕事への活かし方と、未来の可能性を見つけるヒント
「競争性」をキャリアチェンジに活かすヒント
あなたの「競争性」は、新たなキャリアへ踏み出し、自分に本当に合った仕事を見つける際にも、大きな武器となります。
では、どんなステージ(職場)が「競争性」のあなたに合っているのでしょうか。
💡「競争性」が活きるステージ
✅ パフォーマンスが明確な数字で測定され、評価される仕事
営業や販売、マーケティングなど、成果が数値やランキングとして見える職場。
あなたの「勝ちたい」というエネルギーが日々の推進力となり、順位を上げていく過程そのものがモチベーションになります。
✅ 年齢や経験に関係なく、実力で正当に評価される風土
成果を出せば、年齢に関わらずチャンスが与えられるような、実力主義を徹底している組織。
あなたの挑戦心が「次はもっと上へ」という健全な野心に変わり、成長を続ける原動力となるでしょう。
「競争性」の魅力を活したキャリアチェンジを考えたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
よろしければ、ぜひ合わせてご覧ください。
>> 【競争性】転職成功の秘訣!強みを活かす適職探しと自己PR術
人間関係を豊かにする「競争性」コミュニケーション
「競争性」は、人間関係においても、健全な刺激と成長をもたらす、エネルギッシュな資質です。
あなたが持つ「もっと上を目指したい」という情熱が、友人や仲間との間に「一緒に高め合おう」というポジティブな関係性を築きます。
💡「競争性」が活きるコミュニケーション
✅ 共通の目標を「楽しい勝負」に変える
資格試験の勉強や運動など、同じ目標を持つ仲間がいるときは、「どっちが先に達成できるか勝負しよう」と遊び心を交えて競い合ってみましょう。
一人では途中で諦めそうな挑戦も、その勝負が励みとなり、最後まで楽しんでやり抜く力につながります。
✅ 相手の「勝利」を、心からの敬意を込めて称賛する
友人や同僚に先を越されたときには、「今回は完敗だよ、おめでとう」と、心からの敬意を込めて称賛しましょう。
その素直な言葉が、相手に「良きライバル」としての信頼を抱かせ、関係性をより深くしていきます。
あなたの「競争性」は、馴れ合いではなく、お互いを刺激し、高め合える関係を築く力になります。
意識して使ってみると、思っていた以上の尊敬と友情が生まれるかもしれません。
ストレングスファインダー「競争性」に関するよくある質問(FAQ)
ここでは、「競争性」についてよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
A. 「競争性」と対照的な価値観を持つ資質として、「調和性(Harmony)」が挙げられます。
「競争性」は、他者に「勝つ」ことで自らの価値を証明し、その勝利の喜びをモチベーションに変えます。
一方「調和性」は、他者と協力して「合意する」ことで対立を避け、チームに安定感をもたらします。
【チームへのアプローチの違い】
・競争性: 競争を促す。勝利を目指し、エネルギーを生む
・調和性: 協力を促す。合意を目指し、安定感を生む
このように、アプローチは対照的ですが、パフォーマンスレベルを引き上げる力(競争性)と、チームの和を保つ力(調和性)は、どちらも組織には欠かせない要素です。
A. ストレングスファインダーの資質は、他の上位資質と組み合わさることで、強みの現れ方が大きく変わります。
「競争性」の場合、他の資質の活動に対して、「一番になる」という明確な動機を与え、そのパフォーマンスを最大限に引き出す「着火剤」の役割を果たします。
例えば、以下のようなイメージです。
・「競争性」×「達成欲」:
たくさんのタスクをこなしたいというエネルギーに、「誰よりも多く成果を上げたい」という比較対象が加わることで、生産性が飛躍的に高まり、圧倒的な結果を生み出します。
・「競争性」×「最上志向」:
単に勝つだけでなく、「最高のパフォーマンスで」勝利することにこだわり、他の追随を許さないレベルの完成度や成果を追求します。
このように、ご自身の上位資質がどのように掛け合わさっているかを意識することで、あなただけのユニークな強みの活かし方が見えてきます。
まとめ:ストレングスファインダー「競争性」を活かし、自分らしい人生を描こう
「競争性」は、「勝ちたい」という強い情熱をエネルギーに変え、常に自分を高め続けることができる素晴らしい才能です。
その勝利への渇望は、あなた自身の成長を加速させるだけでなく、周囲にとっても「挑戦意欲を引き出す存在」となります。
ぜひ、この素晴らしい力を信じて、日々の選択や行動の中に意識的に取り入れてみてください。
もちろん、資質の活かし方に「正解」はありません。
今回ご紹介したヒントは、あくまで可能性のひとつです。
大切なのは、あなたが心地よく、そして最も自分らしく輝ける方法を、ご自身のペースで見つけていくことです。
ぜひ、「自分らしい競争性の活かし方」を見つけていってください。
あなたの「競争性」が、あなた自身とあなたの周りの世界を、もっと素敵に変えていくことを心から応援しています。
Use your strengths to be yourself.
~強みを活かして、あなたらしい人生を~
【合わせて読みたい「競争性」の関連記事】
・【競争性】キャリアの羅針盤:今の仕事への活かし方と、未来の可能性を見つけるヒント
・【競争性】転職成功の秘訣!強みを活かす適職探しと自己PR術
▼全34資質 解説記事一覧はこちら▼
| 実行力 | 影響力 | 人間関係 構築力 |
戦略的 思考力 |
|---|---|---|---|
| 達成欲 | 活発性 | 適応性 | 分析思考 |
| アレンジ | 指令性 | 運命思考 | 原点思考 |
| 信念 | コミュニケーション | 成長促進 | 未来志向 |
| 公平性 | 競争性 | 共感性 | 着想 |
| 慎重さ | 最上志向 | 調和性 | 収集心 |
| 規律性 | 自己確信 | 包含 | 内省 |
| 目標志向 | 自我 | 個別化 | 学習欲 |
| 責任感 | 社交性 | ポジティブ | 戦略性 |
| 回復志向 | 親密性 |
『ストレングスファインダー』は長年親しまれてきた名称ですが、現在は開発者の名を冠した『クリフトンストレングス®︎』が正式名称として使われています(提供元は変わらずGallup社)。
診断内容や考え方は同じものです。
この記事では、広く知られている『ストレングスファインダー』という言葉を用いますが、現在の正式名称は『クリフトンストレングス®︎』である点をご理解いただけますと幸いです。